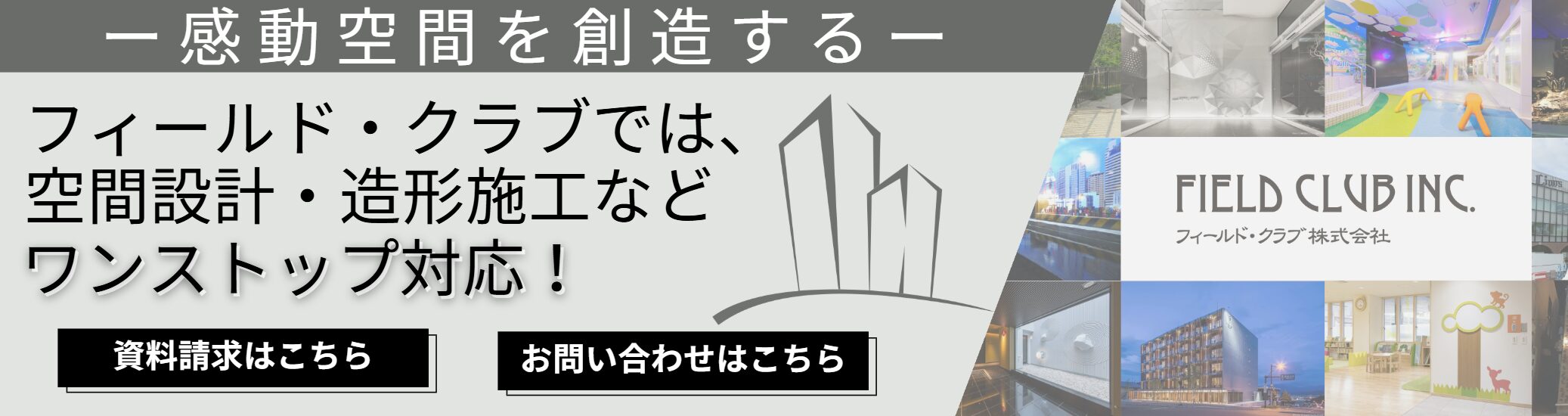BIM建築とは?建築プロセスがどう変わるのかを解説
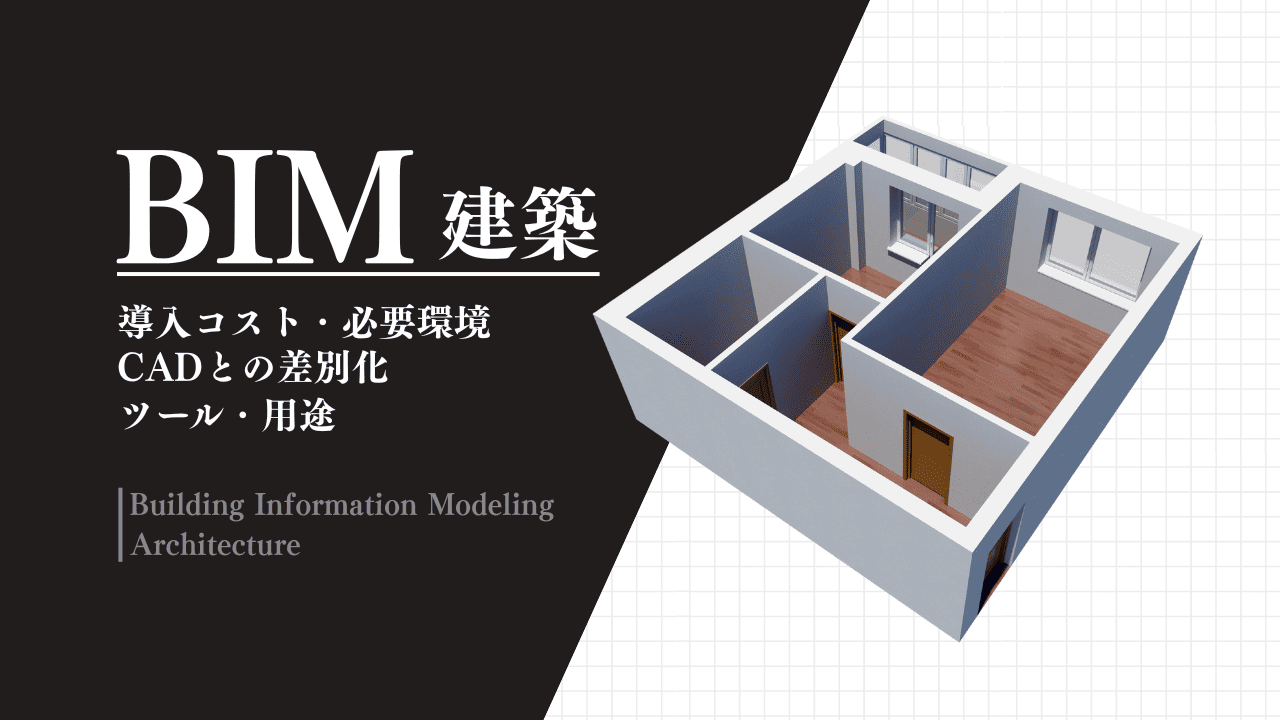
BIM建築とは、建物の形状だけでなく、材料・数量・設備仕様などの情報を一つのモデルに統合し、建築プロセス全体を可視化・管理するための手法です。従来の2次元図面では把握しきれなかった情報を立体的かつデータとして扱えるため、建築の計画・設計・施工・維持管理まで、多くの工程で精度と効率が向上します。
近年では、大規模建築から中小規模のプロジェクトまでBIM建築の活用が広がり、
「どの工程が効率化されるのか」「実際に何が変わるのか」といった疑問も高まっています。
本記事では、BIM建築とは何か、従来の建築プロセスと何が違うのか、そして実際の現場でどんな変化が生まれているのか をわかりやすく解説します。BIM建築を理解し、業務改善に役立てたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
空間づくりで失敗したくない方へ
- イメージはあるが、どう形にすればいいかわからない
- 設計意図が現場に伝わらず、仕上がりにズレが出た
- 素材・工法選びで後悔したくない
空間づくりでは「企画・デザイン・設計・造形・施工」を分断するのは非合理的です。 工程の分断は失敗と遅延の原因となり結果的に異なる空間になる可能があります。
フィールド・クラブでは、空間の企画段階からデザイン・設計・造形・施工までを 一貫して対応し、「イメージ通り」と「現場で成立する」を両立した 空間づくりを実現します。
「まだ具体的に決まっていない」「まず相談だけしたい」 という段階でも問題ありません。まずは お気軽にご相談ください。
お客様に寄り添った空間づくりを、提供いたします。
BIM建築とは?建築プロセスを支える情報管理手法
BIM建築とは、建物の形状だけでなく、部材寸法・数量・設備仕様・仕上げ情報など、建築に関わる幅広い情報を一つのモデルに統合して管理する手法です。従来の2次元図面では断片的に扱われていた情報を、3Dモデルと属性データとして整理・可視化できるため、建築プロセス全体で整合性と精度が向上します。
BIMモデルには設計・施工・維持管理に必要な情報が格納され、図面・工程・コスト・数量といったデータを一元的に扱える点が大きな特徴です。建築プロジェクトで頻発していた「情報の重複」「伝達ミス」「手戻り」を防ぎ、関係者が同じデータを参照しながら意思決定できる仕組みが整います。
また、クラウド環境やモバイル端末との連携により、現場での情報更新や図面確認がスムーズになり、施工管理や設備保全といった後工程でもBIMデータを活用できます。このような点からBIM建築は、建物のライフサイクル全体を通して情報を活かす“建築DXの基盤”として重要性が向上中です。
BIM建築で何ができる?建築プロセスが変わる4つのポイント

BIM建築では、建物に関する情報をモデルに集約することで、設計・施工・維持管理の精度と効率が大きく向上します。従来はバラバラに扱われていた情報が一体化されることで、建築プロセス全体が“見える化”され、判断ミスや手戻りの削減につながります。
ここでは、BIM建築が建設プロジェクトにもたらす代表的な機能を紹介します。
1.情報を統合した3Dモデリング
BIM建築の基盤となるのが、形状+属性情報を持つ「情報付き3Dモデル」 です。
建物の形状 / 部材寸法 / 仕上げ / 材料 / 設備仕様
これらの情報をまとめて管理できるため、設計段階から完成イメージの共有が容易になり、建築プロジェクトの意思決定がスムーズになります。
2.衝突・干渉の自動検知
BIMモデルを使うと、配管・梁・ダクトなどの干渉(クラッシュ)を自動検出できます。
・「梁に配管がぶつかる」
・「天井高さが確保できない」
・「点検スペースが不足している」
こうした問題を設計段階で発見できるため、施工中のやり直しやコスト増加を大幅に減らせます。
3.工期・コストの連動シミュレーション
BIM建築では、モデルに「時間(4D)」「コスト(5D)」を付与できます。
・工程表とモデルを連動させた工期シミュレーション
・数量拾いの自動化
・見積り作成の効率化
・設計変更の影響を即時把握
など、プロジェクト全体の計画精度が向上します。関係者全員が同じ情報をリアルタイムで確認できるため、情報共有のバラつきがなくなり、意思決定が早くなる点もメリットです。
4.設計・施工・維持管理までの情報連携
BIM建築の大きな特徴は、設計データを施工・維持管理まで引き継げることです。
・施工時の現場管理
・設備点検
・修繕計画
・経年劣化の記録
・更新時の判断材料
BIMデータは建物の“デジタル資産”として活用され、建築のライフサイクル全体で効率化をもたらします。
▼その他BIMについては以下の記事をご覧ください▼
https://fieldclub.co.jp/column/bim-spatial-design/
BIM建築のメリット
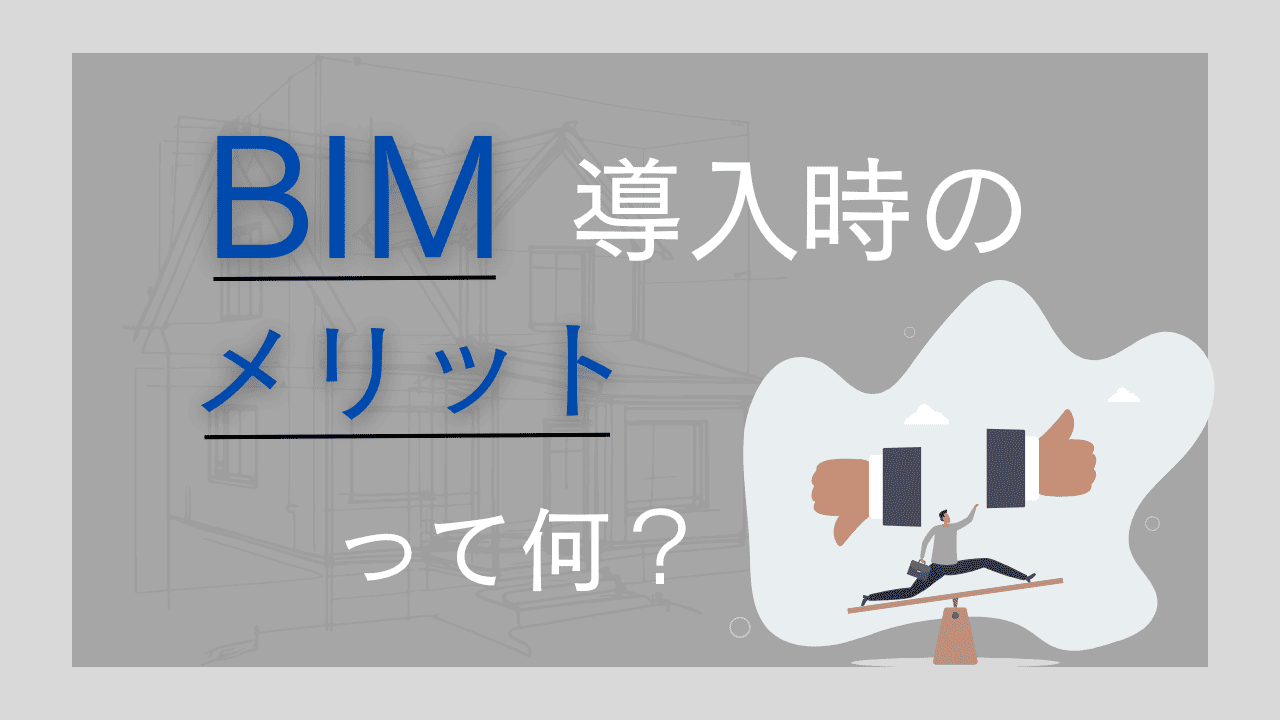
BIM建築では、建物に関する情報を一元的に扱えるため、設計・施工・維持管理のすべての工程で精度と効率が向上します。
従来は図面・数量・工程が別管理だったために起きていたミスや手戻りを減らし、建築プロジェクト全体の生産性向上につながります。ここでは、BIM建築がもたらす主なメリットを紹介します。
1.設計の精度を高め、合意形成が早く進む
BIMの大きな利点は、形状や仕様を立体情報として一目で共有できる点です。
発注者・設計者・施工者が同じモデルを見ながら判断できるため、初期段階での認識ズレが起きにくく、検討のスピードが格段に上がります。
2施工トラブルを事前に察知し、現場の混乱を防ぐ
配管と梁の衝突、点検口の不足など、従来なら「現場で気づく」問題を、BIMは設計時点で洗い出します。事前に対策できるため、工程遅延や追加工事といったコスト負担を軽減できます。
3.工期・コスト管理が“見える化”し、意思決定がしやすくなる
工程(4D)やコスト(5D)をモデルに紐づけることで、
「この変更が工期にどう影響するか」「コストがどう動くか」を即座に把握できます。
数字と空間情報が結びつくため、関係者全員の判断根拠が揃います。
4.建物のライフサイクル全体で情報が活かせる
完成後も、設備仕様・部材位置・修繕履歴などをモデルに残せます。長期の維持管理や更新計画が立てやすく、建物の“デジタル資産”として活用できる点はBIMならではです。
5.チームワークが向上し、プロジェクト全体がスムーズに回る
クラウド連携により、最新情報が常に共有されます。「どれが最新図か」「誰が更新したか」の確認が不要になり、部門間のコミュニケーションが格段に改善されます。
6.次世代技術との連携で、建築DXの基盤になる
BIMデータはAI解析、IoTセンサー連携、VR/AR確認など、さまざまな先端技術と相性が良いのが特徴です。デジタルツインやスマートシティなど、今後の建築DXを支える“中心技術”として期待されています。
主要BIMソフトの違いを解説
BIMシステムを導入する際には、自社の設計・施工・維持管理体制に合ったソフト選びが重要です。ここでは国内外で代表的なBIMソフトを挙げ、それぞれの特徴と選び方のポイントを整理します。
1.Revit(Autodesk社):幅広い分野対応・大規模プロジェクト向け
Revitは設計・構造・設備・施工の各フェーズに対応し、大規模なゼネコン/設計組織でも導入実績が豊富です。データベース機能が優れており、設備品番・部材属性管理などが可能です。Windows限定という動作環境の注意点があります。
2.Archicad(GRAPHISOFT社)/BIMx連携:デザイン重視・Mac対応あり
Archicadは3Dベース設計に強く、デザイン事務所や建築設計事務所での利用が多く、MacOSにも対応しています。BIMxアプリとの連携で3Dモデルをクライアント共有しやすい点も特徴です。買い切りライセンスを選ぶ場合が多く、初期コスト設計に適しています。
3.GLOOBE(福井コンピュータアーキテクト株式会社):日本法規寄り・確認申請まで対応
GLOOBEは日本建築法規(斜線制限・容積算定等)に則った機能が豊富で、企画段階〜確認申請〜維持管理まで一貫して使えるBIMとして評価されています。Windows環境が前提です。
4.Vectorworks(Vectorworks社/A&A 日本代理):2DCADからの移行・中小規模向け
元々2D CADとして定評があったVectorworksは、BIM機能を追加し、操作性・馴染みやすさに優れています。インテリア、ランドスケープ、照明計画など用途の広さも特徴で、中小規模設計事務所での導入例が多いです。Windows・Mac両対応。
5.選び方のポイント:プロジェクト規模・目的・既存環境を軸に判断
プロジェクトの規模(大手〜中小)、目的(設計重視・施工含む・維持管理含む)、既存のIT環境(Windows/Mac・他CADとの連携)を軸にソフトを選定すべきです。さらに、コスト(サブスク vs 買切り)、学習コスト、社内運用体制も考慮対象です。
導入時の注意点と問題点
BIM導入にはメリットが多いですが導入する際には注意が必要な点がいくつかあります。あらかじめ知っておき対策しておきましょう。
初期投資のコスト
BIMの導入にはソフトウェア、環境整備、研修などで特に初期費用で大きくコストがかかります。また、すぐに効果が出るわけではなく短期的なコスト増を見越した上で、中期的なメリットとのバランスを考える必要があります。
ITリテラシーが大切
BIMは高度なデジタルツールであるため、スタッフのITリテラシーが導入の成否を大きく左右します。基本的なPCスキルやクラウド利用に不慣れな場合、導入がスムーズに進まないこともあります。また「従来のやり方とのギャップ」に戸惑い、抵抗感がでるケースもあるため、教育・サポート体制を整える事が重要です。
その他の課題
- データ共有体制の整備:関係者間でのデータ形式や管理ルールを統一しないと、情報が活かしきれない
- 短期的な生産性低下:導入直後は操作に慣れるまで業務効率が下がる可能性がある。
- 経営層の理解不足:現場だけでなく経営層もBIMの価値を理解し、投資判断や社内推進をサポートする必要がある。
BIM建築のことならフィールド・クラブへ
BIMは設計から施工、維持管理まで一元管理できる次世代の建築ツールです。導入には初期コストや教育体制の整備が必要ですが、長期的には工期の短縮やコスト削減、品質向上といった大きなメリットをもたらします。さらにAI・IoT・XR、国際基準との連携により今後ますます進化していくと期待されています。
フィールド・クラブでは、BIMを活用した設計・施工の効率化をサポートしています。
BIMの導入や、BIMを用いた建築を検討される方は、ぜひお気軽にご相談ください。