インクジェット看板とは?仕組み・素材・耐久性・コストまで解説
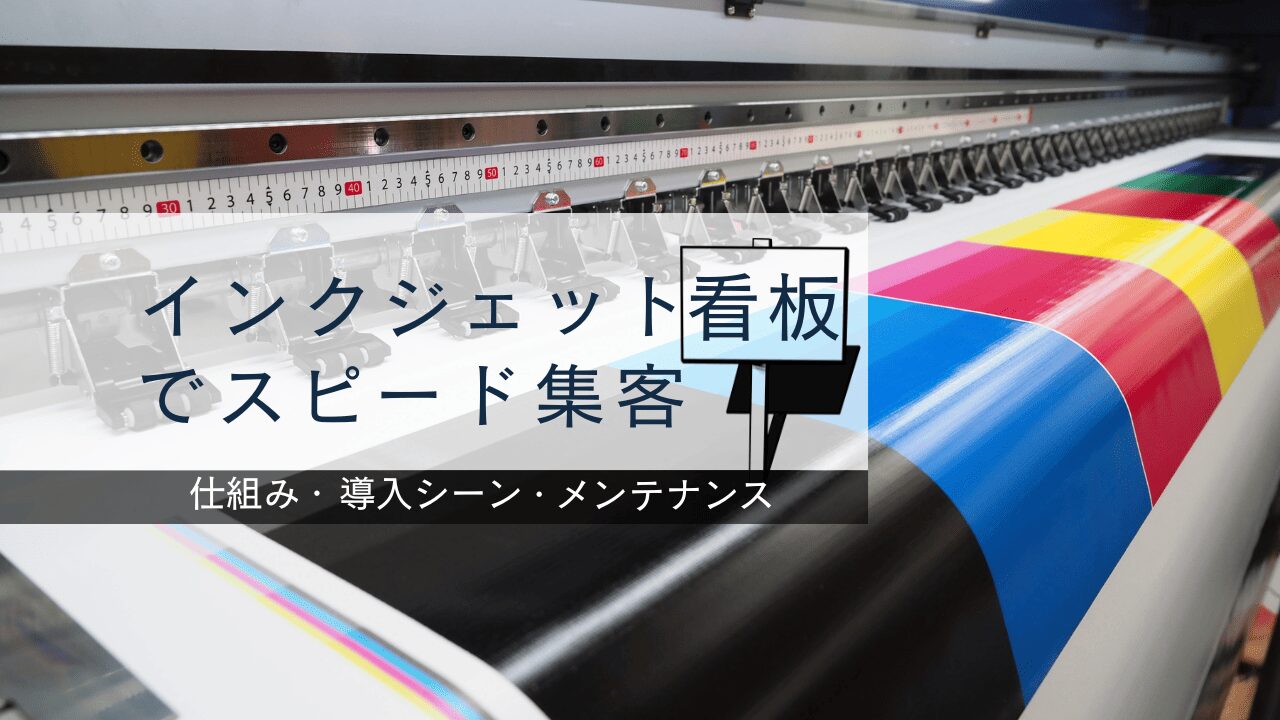
店舗や施設の顔ともいえる「看板」。その中でも、近年主流となっているのがフルカラー印刷が可能なインクジェット看板です。デジタル印刷技術によって、写真やグラデーションなどの繊細なデザインを高精度に再現できるうえ、版の作成が不要なため短納期・小ロット対応が可能。コストを抑えながら高品質なビジュアル表現を実現できる点が大きな魅力です。
本記事では、インクジェット看板の仕組み・素材・耐久性・導入シーンまでをわかりやすく解説していますので看板の種類選びやリニューアルを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
インクジェット看板とは?

インクジェット看板とは、デジタル印刷機を使ってシートや素材に直接フルカラーで印刷を行う看板のことです。
写真やグラデーションなどの細かな色表現が可能で、デザインの自由度が非常に高い点が特徴となっています。
従来の印刷方式と異なり、版の作成が不要なため、データ入稿だけで短期間の製作ができ、1枚からの小ロットにも対応できます。急な開店準備やイベント用の短期制作にも柔軟に対応できるため多くの場面で活躍中です。また、屋外看板・店舗サイン・ウィンドウ装飾・イベントバナーなど、用途の幅が広く、商業施設や展示会、企業ブランディングなどさまざまなシーンで採用されており、高精細な印刷によってブランドロゴや写真を美しく表現する事が可能となっています。
カッティングシートとの違い
インクジェット看板とよく比較されるのが「カッティングシート」です。どちらも看板やサイン制作に用いられますが、印刷方式・表現力・用途の幅に大きな違いがあります。
カッティングシートは、単色の塩ビフィルムを文字やロゴの形に切り抜いて貼り付けるタイプの看板で、シンプルで視認性が高く、社名や営業時間などの案内表示に適しています。
一方、インクジェット看板はフルカラー印刷で写真やグラデーション、立体的な表現も可能なため、訴求力やデザイン性に優れています。また、インクジェット方式は版の作成が不要で、データをそのまま出力できるのが特徴で、デザインの修正や増刷にもスピーディーに対応でき、短期イベントから屋外の大型サインまで幅広い用途に対応します。
デザイン性を重視したい場合や、多彩な色表現が求められる看板では、カッティングシートよりもインクジェット看板が適切と覚えておきましょう。
インクジェット看板の導入シーン例

インクジェット看板は、デザインの自由度と短納期対応を活かして、あらゆる業種・空間で活用できる看板として広く導入されています。ここでは代表的な活用シーンを紹介します。
まず代表的なのが店舗看板やファサードサインです。ショップロゴや商品写真を大きく印刷でき、通行人の目を引くビジュアル訴求が可能で、印刷の発色が良いため、ブランドイメージの再現にも向いています。
イベントや展示会装飾では、軽量で持ち運びしやすい素材を使用できるため、設置・撤去が簡単です。短期利用でも高品質な印刷ができ、企業ブースやプロモーション用のビジュアルとしても重宝されます。施設案内板や誘導サインでは、シンプルな文字情報だけでなく、地図やピクトグラムを組み合わせたわかりやすいデザインを実現し視認性とデザイン性を両立できます。
また、電飾看板ではFFシートとUV印刷の組み合わせにより、夜間でも発色を維持し、明るく鮮明な印象を与えます。飲食店や商業施設の外観演出に最適です。さらにウィンドウサインやガラス装飾にも応用でき、透明シートや乳半シートを使うことで、光を活かした空間演出が可能です。季節やキャンペーンごとに貼り替えも簡単で、デザイン更新も容易です。
このように、インクジェット看板は短期イベントから長期常設サインまで柔軟に対応できる汎用性の高さが人気の理由で、目的や環境に応じた最適な素材・印刷方式を選ぶことで、デザイン性と実用性を兼ね備えた理想のサイン表現が実現可能となります。
インクジェット看板に使われる素材一覧と特徴
インクジェット看板には、設置場所や目的に応じてさまざまな素材が使われます。それぞれに特徴や適した用途があり、環境や表示期間によって選び分けることが重要です。
塩ビシート(PVC)
屋外・屋内どちらにも対応でき、防水性・耐久性・コストのバランスに優れている万能素材です。
壁面やガラス面、アルミ複合板などに貼るプレート看板として広く利用されています。
ターポリン
ビニール繊維を織り込んだ布状の柔軟素材で、防水性と軽量性を兼ね備えています。
折りたたみが可能で持ち運びやすく、イベント会場のバナーや横断幕、短期装飾などに最適です。
FFシート(フレキシブルフェイス)
光を透過する電飾用のシートで、夜間でも明るく鮮やかに表示できるのが特徴です。
内照式看板やライトボックスなど、照明を使ったサインに多く採用されています。
PETシートや紙ベース素材
軽量でコストを抑えられる反面、耐候性は低いため屋内限定の使用に適しています。展示会やポスター、短期イベント装飾など、期間限定の掲示に向いています。
透明シートや乳半シート
この二種類のシートは、ガラス面の装飾に最適です。透明シートは視界を確保しつつデザインを表現でき、乳半シートは白く半透明な質感で光をやわらかく拡散させ、照明付き看板やウィンドウサインに効果的です。
このように、インクジェット看板は素材ごとに特性が異なるため、設置場所・使用期間・演出効果に合わせて選ぶことが、見た目と耐久性を両立するポイントです。
メンテナンス・耐久性・寿命

インクジェット看板の耐用年数は、設置環境や素材の種類、施工品質によって異なりますが、一般的な屋外使用では3〜5年程度が目安とされています。直射日光や風雨にさらされる環境では劣化が早まるため、適切なメンテナンスと設置計画が重要です。
・ラミネート加工
劣化の主な原因は紫外線・雨・熱です。これらはインクの退色やシートの伸縮・剥がれを引き起こすため、ラミネート加工による表面保護が効果的です。光沢タイプなら発色をより鮮やかに、マットタイプなら反射を抑え落ち着いた印象を与えつつ、いずれも耐久性を高められます。
・定期的な清掃
定期的な清掃も長持ちのポイントです。ホコリや排気ガスなどの汚れを放置すると、表面の劣化や色あせの原因になります。柔らかい布や中性洗剤でやさしく拭くだけでも、発色を維持しやすくなります。
・施工時の下処理
施工時の下地処理や圧着の精度も寿命を左右します。貼付け面の油分やホコリを十分に除去し、均一に圧着することで、粘着力を保ち剥がれを防止できます。さらに、軒下や日陰など直射日光の少ない場所に設置することで、より長期間美しい状態を保てます。
インクジェット看板を長く使うためには、素材の選定と施工品質、そして定期的なメンテナンスの3点をバランス良く行うことが大切です。
インクジェット看板のコストと費用構成
インクジェット看板の費用は、デザインの複雑さ・使用素材・施工方法などによって変わります。
製作工程ごとの内訳を理解しておくと、見積もりの比較やコスト調整がしやすくなります。
主な費用の内訳
・デザイン費
レイアウト・色調整・ロゴ配置など、印刷データを作成・修正する費用です。既存データがある場合はこの部分を抑えられます。
・印刷費
出力サイズや使用インクの種類によって決まります。高発色や長期耐候インクを使用する場合はやや高くなる傾向があります。
・素材費
塩ビシート、ターポリン、FFシートなど、使用する素材ごとに価格帯が異なります。屋外長期使用向けほどコストは上がりますが、その分耐久性が高まります。
・ラミネート-加工費
印刷面を保護するためのラミネートや、カット・防汚・防水などの追加加工にかかる費用です。長期使用を前提とする場合は省略しないのが基本です。
・施工費
現場での貼り付けや取付け工事に要する費用です。設置場所の高さや環境、看板の大きさによって変動します。
コストを抑えるポイント
・既存デザインデータを活用して制作時間を短縮する。
・同素材・同サイズをまとめて発注し、印刷効率を高める。
・使用期間に応じた素材選定を行い、短期用途に高コスト素材を使わない。
・ラミネート加工を省略しないことで、長期的な再施工リスクを防ぐ。
コストを単純に削減するよりも、「目的・耐久性・見栄え」のバランスを意識して計画することで、結果的にトータルコストを抑えた看板運用が可能になります。
看板インクジェットについてフィールド・クラブへご相談ください!
インクジェット看板は、高精細な印刷表現と柔軟な対応力を兼ね備えた、現代の看板制作に欠かせない手法です。素材や仕上げの選び方次第で、屋外でも長期間美しさを保てるうえ、写真やグラデーションを活かしたデザインで高い訴求効果を発揮します。
短期イベントから店舗ファサード、電飾サインまで用途は幅広く、コスト・耐久性・デザイン性のバランスを取りやすい点も魅力です。定期的なメンテナンスや設置環境への配慮を行うことで、長期的にも高いパフォーマンスを維持できます。
フィールド・クラブでは、デザインから施工までを一貫して行い、目的や環境に合わせた最適な看板プランをご提案しています。
看板の新設やリニューアルを検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。