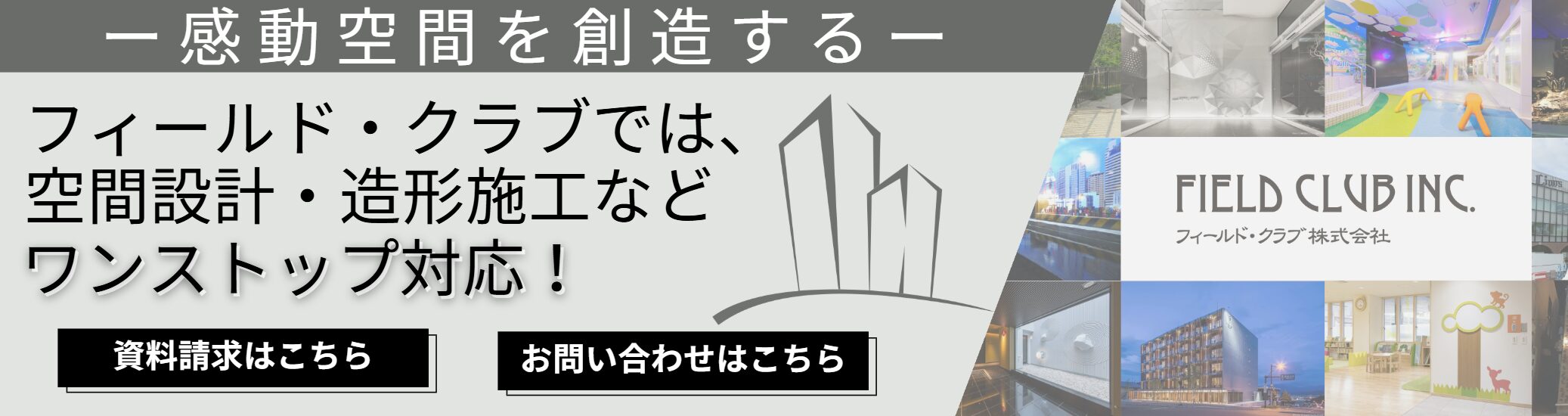コンクリートとモルタルの違いとは?特徴・使い分け・使用する際の注意点を解説!

コンクリートとモルタルは、いずれも建築現場で欠かせない素材ですが、その特徴や用途は大きく異なります。住宅の基礎や外構、仕上げ材として使い分けを誤ると、耐久性や美観に影響を及ぼすこともあります。
本記事では、コンクリートとモルタルの基本的な違いから、それぞれの適切な活用シーン、施工時に注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。建築やリフォームを検討している方や設計・施工に携わる方にとって、実務に役立つ知識を整理してご紹介します。
空間づくりで失敗したくない方へ
- イメージはあるが、どう形にすればいいかわからない
- 設計意図が現場に伝わらず、仕上がりにズレが出た
- 素材・工法選びで後悔したくない
空間づくりでは「企画・デザイン・設計・造形・施工」を分断するのは非合理的です。 工程の分断は失敗と遅延の原因となり結果的に異なる空間になる可能があります。
フィールド・クラブでは、空間の企画段階からデザイン・設計・造形・施工までを 一貫して対応し、「イメージ通り」と「現場で成立する」を両立した 空間づくりを実現します。
「まだ具体的に決まっていない」「まず相談だけしたい」 という段階でも問題ありません。まずは お気軽にご相談ください。
お客様に寄り添った空間づくりを、提供いたします。
コンクリートとモルタルの違いを簡単に解説
建築現場で頻繁に登場する「コンクリート」と「モルタル」。どちらもセメントを基材とした建材ですが、混合される材料の違いによって性質や用途が大きく変わります。ここでは、それぞれの特徴を整理して見ていきましょう。
コンクリート

コンクリートは、セメント・砂・砂利(砕石)・水を混合してつくられる建材です。砂利を含むため圧縮強度に優れ、建物の基礎・柱・梁・道路など、構造体を支える大規模工事に欠かせません。高い耐久性を備えているため、長期間にわたり使用できる点が大きな強みです。
モルタル

モルタルは、セメント・砂・水を混合してつくられる建材です。砂利などの粗骨材を含まないため仕上がりがきめ細かく、壁の下地やタイルの接着材、補修材として利用されます。細やかな仕上げが可能で、比較的扱いやすいためDIY用途にも広く用いられています。
強度・耐久性の違い
建築に広く用いられるモルタルとコンクリートは、材料構成の違いから強度や耐久性に明確な差があります。ここでは圧縮強度、ひび割れやすさ、長期耐久性の観点で比較していきます。
圧縮強度の比較
モルタルはセメントと砂のみで構成されるため、圧縮強度は数十N/mm²程度にとどまります。小規模な施工や仕上げ材としては十分ですが、構造体を支える強度はありません。
一方コンクリートは砂利や砕石といった粗骨材を含むことで、一般的に20〜30N/mm²以上の圧縮強度を発揮します。さらに調合や設計次第では高強度コンクリートの仕様も可能で、大規模な構造物に不可欠な建材とされています。モルタルは乾燥収縮が大きく、ひび割れが発生しやすいという弱点があります。さらに粗骨材を含まないため水の浸入にも弱く、耐水性はコンクリートに劣ります。
一方コンクリートは粗骨材によって収縮が抑制されるため、ひび割れや耐水性に優れます。ただし完全にひび割れを防ぐことは難しく、施工精度や養生の質によって性能が大きく左右されます。
ひび割れやすさ・耐水性の違い
モルタルは乾燥収縮が大きく、ひび割れが発生しやすいという弱点があります。さらに粗骨材を含まないため水の浸入にも弱く、耐水性はコンクリートに劣ります。
一方コンクリートは粗骨材によって収縮が抑制されるため、ひび割れや耐水性に優れます。ただし完全にひび割れを防ぐことは難しく、施工精度や養生の質によって性能が大きく左右されます。
長期使用での耐久性
モルタルは補修材や仕上げ材として有効ですが、屋外や長期間の使用では劣化が進みやすい点に注意が必要です。特に外壁仕上げなどでは、雨水や紫外線の影響を受けるため定期的なメンテナンスが欠かせません。
これに対しコンクリートは、適切に施工・管理すれば数十年単位で使用に耐える高い耐久性を発揮します。この特性こそが、コンクリートが大型建築物や道路、橋梁などインフラ工事に採用される最大の理由といえます。
◆フィールド・クラブではご要望に最適な建材をご提案いたします。
建築依頼を検討している方は、ぜひフィールド・クラブへご相談ください。”フィールド・クラブ”をもっと詳しく
モルタルとコンクリートの使い分け
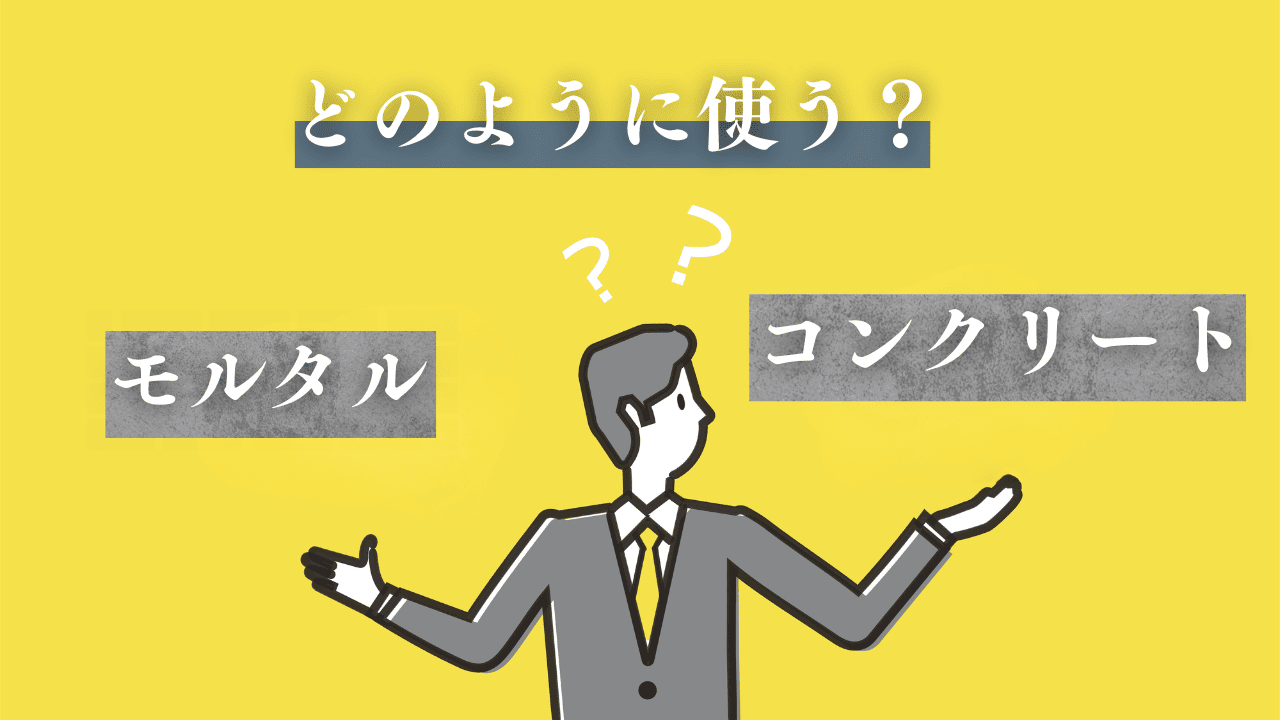
ここまで紹介したように、モルタルとコンクリートは構成材料や性質が異なるため、用途も明確に分かれます。実際の建築現場では、それぞれの特性を活かし適材適所で使い分けることが重要です。
モルタルが使われる場面
●柔軟性があるため、建物の外壁やレンガ、ブロックの接着剤として使用される。
●装飾性が高いので仕上げ材にも適している。
●強度が不十分なので、建物の構造体には使用されない。
左官職人がコテを使って塗り付けるのがモルタルです。モルタルは粗骨材が含まれていないため、柔らかく加工がしやすいので自由度を求められる際に使われます。
コンクリートが使われる場面
●強度が高いため、柱や梁、壁といった建物の構造体に使用される。
●圧縮力に強い一方、引っ張る力に対しては弱い。
●粘性が高いので、加工の自由度は低い。
コンクリートは強度が高いのが特徴ですが、引っ張る力には弱いという難点があります。この弱点をカバーするため、コンクリートの中に鉄筋を入れた「鉄筋コンクリート」が広まったりと耐久性を求められる際に使用されます。
▼モルタル・コンクリートについての参考記事はこちら▼
https://fieldclub.co.jp/column/atificial-rock/
価格・入手方法の違い
ここからは、実際にモルタルやコンクリートを使用したい場合に知っておきたい購入場所と価格の目安について解説します。
モルタルとコンクリートの販売場所
モルタル・コンクリートのいずれも、ホームセンターで袋詰めの商品が販売されています。モルタルは20kg前後の小袋が主流で、すぐに練って使えるインスタントタイプもあり、DIYに最適です。コンクリートも同様に少量タイプが入手可能ですが、本格的な施工で用いられる生コンクリートは、基本的に生コン工場や建材業者を通じて手配する必要があります。
小袋(DIY用)と業務用の価格目安
市販で購入できるモルタル・セメント・生コンクリートの相場を紹介していきます。
●モルタル小袋(20kg前後):約800円~1000円
●インスタントコンクリート小袋(25kg前後):約700円~1000円
●生コンクリート(業務用・1㎥あたり)約25000円~30000円
少量購入ならモルタルや袋入りコンクリートが便利ですが、広い面積を施工する場合は生コンを注文した方が効率的でコストも下がります。
コストパフォーマンスの違い
モルタルは少量から入手できるため、壁の補修や仕上げ作業など無駄なく使用でき経済的です。対して大規模施工ではコンクリートの方がコストパフォーマンスに優れており、特に基礎工事や舗装では袋入りを大量に購入するよりも生コンを手配した方がはるかに割安です。
DIYでの注意点・安全面
モルタルやコンクリートをDIYで扱う際は、材料の性質を理解したうえで作業することが重要です。特に初心者は「練り方」「水分量」「養生(乾燥管理)」で失敗しやすく、安全面への配慮も欠かせません。ここでは具体的な注意点とよくある失敗例をまとめます。
モルタルを使う際の注意点
●練りすぎ・時間管理
モルタルは練りすぎると水分が飛んでしまい、硬化が早まって施工時間が短くなります。
必要な量を小分けで練り、練ったらすぐに使用するのが鉄則です。
●水分量の管理る
水が多すぎると強度が低下し、乾燥後にひび割れが発生しやすくなります。
逆に水が少ないと硬すぎて塗り広げられず、仕上がりが汚くなります。
袋に記載された目安を守りましょう。
●仕上げ時の養生
乾燥が急激に進むとひび割れの原因になります。
直射日光や強風を避け、必要に応じて濡れタオルやビニールで覆って保湿・養生を行うときれいに仕上がります
よくある失敗例
・一度に大量に練って余らせ、固まって使えなくなる
・水を足して再利用しようとし、強度不足を招く
・素手で扱い皮膚が荒れる
コンクリートを使う場合の注意点
●重量と作業環境
コンクリートは砂利を含むため非常に重く、袋を持ち運ぶだけでも体力を使います。
DIYでは20〜25kg袋を複数使用するケースが多いため、腰痛や転倒に注意しましょう。
●硬化熱と作業スピード
コンクリートは化学反応で硬化が進む際に熱を発します。
気温が高い時期は特に硬化が早く進むため、余裕を持った作業計画が必要です。
練った後にダラダラしていると、型枠に流す前に固まってしまうことがあります。
●養生と仕上げ
打設後はすぐに強度が出るわけではなく、数日から数週間かけて徐々に固まります。
施工後は水をかけて乾燥を防いだり、ブルーシートで覆って直射日光や雨を避けたりする「養生」が欠かせません。
これを怠ると表面が粉っぽく崩れたり、ひび割れの原因になります。
よくある失敗例
・1人で広範囲の施工を試み、途中で固まって仕上がりがムラになる
・練る際に水を多めに入れて作業しやすくした結果、硬化後に強度不足となる
・養生を怠り、雨に打たれて表面がボロボロになる
モルタルとコンクリートについてはフィールドクラブへ
モルタルとコンクリートは、同じセメントを基材としながらも「含まれる骨材の有無」によって性質や用途が大きく異なります。
- モルタルは、加工性や仕上がりの美しさに優れ、壁の下地・タイルの接着・補修など細やかな仕上げ用途に最適
- コンクリートは、圧縮強度と耐久性に優れ、建物の基礎や柱、道路・橋梁など大規模で長期使用を前提とした構造材として必須
価格面でも、モルタルは少量購入がしやすくDIYや補修向き、コンクリートは生コンを大量に使用する大規模工事においてコスト効率を発揮します。
建築やリフォームでモルタルとコンクリートをどう使い分けるかを理解することは、建物の美観と寿命を大きく左右します。適材適所で正しく選び、長く安心して利用できる空間づくりを目指しましょう。
本格的な施工や大規模プロジェクトをご検討中の方は、ぜひフィールド・クラブにご相談ください。企画から設計デザイン、製作、施工、管理までをワンストップでご提供し、商業施設や公共建築、看板や造形物など幅広い分野で高品質な建築デザインを実現いたします。